児童扶養手当
最終更新日:2025年9月17日
ページID:5432
ここから本文です。
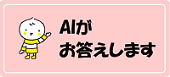
- お知らせ
- 児童扶養手当について
- 対象となる児童・申請者
- 所得制限限度額
- 手当額(月額)
- 申請・支給の方法
- 受給開始後の手続き
- マイナンバー(個人番号)および本人確認
- よくある質問
- ご注意
- その他の手当
- 問い合わせ先
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を育てている方に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
児童扶養手当のてびき【2025年4月改定版】(PDF:1,023KB)
対象となる児童及び申請者
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(政令で定める中度以上の障害の状態にある場合は20歳未満)の児童(以下「児童」という)について、その児童を監護している母、その児童を監護し生計を同じくする父、父母にかわって児童を養育している養育者に支給されます。(養育者が複数いるときは、その家庭の生計の中心となっている人が請求者となります。)
※監護…監督し、保護すること
※養育…児童と同居し、監護し、生計を維持していること
対象となる児童
- 父母が婚姻(内縁関係を含む)を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める重度障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児など父母が明らかでない児童
ただし、次のいずれかにあてはまるときは手当を支給できません。
支給されない場合
- 手当を受けようとする者(母、父または養育者。以下「申請者」という)もしくは児童が、日本国内に住所がない場合。
- 児童が里親に委託されている場合。
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)等に入所している場合。
- 児童が父の配偶者又は母の配偶者に養育されている場合。ただし、配偶者が政令で定める重度障害の状態にある母または父である場合を除く。(配偶者は戸籍上婚姻関係になくても、事実上婚姻関係と同様の状態にある者を含む)
- 申請者が母または養育者のときは、児童が父と生計を同じくしている場合。ただし、父が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く。
- 申請者が父のときは、児童が母と生計を同じくしている場合。ただし、母が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く。
所得制限限度額
この手当は、申請者及び生計を共にする扶養義務者等(申請者の配偶者、生計同一の直系血族及び兄弟姉妹)の所得により支給額が決まります。
また、扶養義務者等の所得が制限限度額以上の場合は支給停止となります。
※所得は合算ではなく、申請者・扶養義務者等のそれぞれの所得で判定します。
※世帯分離をしていても、同居し生計を共にしている場合は扶養義務者等として所得の判定を行います。
※児童扶養手当の年度は11月~翌月10月となります。
例)申請が2025年4~9月の場合は、2024年度所得(2023年1~12月の所得・養育費)、 2025年10月~2026年3月の場合は、2025年度所得(2024年1~12月の所得・養育費)で 支給額を計算します。
| 児童扶養手当上の所得額=(前年の総所得金額+養育費の8割)-下記の控除額 |
控除額
- 基礎控除への振替・・・・・10万円(給与所得及び公的年金等所得の合計が10万未満の場合はその額)※自営業の所得には適用されません
- 一律控除・・・・・・・・・8万円
- 障害者控除・・・・・・・・1人につき27万円
- 特別障害者控除・・・・・・1人につき40万円
- 勤労学生控除・・・・・・・27万円
- 寡婦控除・・・・・・・・・27万円(申請者が母の場合は控除しない)
- ひとり親控除・・・・・・・35万円(申請者が父または母の場合は控除しない)
- 医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除・・・実額
損益通算・繰越控除・分離課税などがある場合は、計算方法が異なることがあります。
所得制限限度額
| 扶養親族等数 | 申請者 |
扶養義務者等
(金額:未満)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部支給 (金額:未満) |
一部支給 (金額:未満) |
|||||
| 所得ベース |
【参考】※ |
所得ベース | 【参考】※ 収入ベース |
所得ベース | 【参考】 収入ベース |
|
|
0人 |
69万円 | 142万円 | 208万円 | 334.3万円 | 236万円 | 372.5万円 |
| 1人 | 107万円 | 190万円 | 246万円 | 385万円 | 274万円 | 420万円 |
| 2人 | 145万円 | 244.3万円 | 284万円 | 432.5万円 | 312万円 | 467.5万円 |
| 3人 | 183万円 | 298.6万円 | 322万円 | 480万円 | 350万円 | 515万円 |
| 4人 | 221万円 | 352.9万円 | 360万円 | 527.5万円 | 388万円 | 562.5万円 |
| 5人 | 259万円 | 401.3万円 | 398万円 | 575万円 | 426万円 | 610万円 |
所得額・扶養親族等の数は、原則、住民税課税台帳上のものによります。扶養親族等でない児童を前年の12月31日に監護・生計維持していた場合は、申立の上、扶養親族等数に含めることができる場合があります。
※収入ベースの金額については、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した金額であり、その他の所得では金額が異なる場合もあります。
所得制限限度額への加算
<申請者>
- 同一世帯配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族・・・1人につき10万円
- 特定扶養親族(19歳~22歳)・・・・・・・・・・・・・・・1人につき15万円
- 16歳~18歳までで申立書がある扶養親族・・・・・・・・・・1人につき15万円
<扶養義務者等>
- 老人扶養親族・・・1人につき6万円 ※老人扶養親族のほかに扶養親族等がいない場合は1人を除く
手当額(月額)【2025年4月~】
手当額は、消費者物価指数の変動等に応じて改定されます。次回は2026年4月分手当から変更が予定されています。(物価スライド制)
| 児童数 | 全部支給額 | 一部支給額・計算式 |
| 1人目 | 46,690円 | 46,680円~11,010円(所得に応じて決定されます) 46,680円-(申請者の所得額-所得制限限度額※1)×0.0256619※2 |
| 2人目以降加算額 | 11,030円 | 11,020円~5,520円(所得に応じて決定されます) 11,020円-(申請者の所得額-所得制限限度額※1)×0.0039568※2 |
※1 所得制限限度額・・・所得制限限度額表の「申請者の全部支給の所得制限限度額」
※2 端数処理・・・10円未満四捨五入
・一部支給額は所得に応じて決定されます。
・年金受給者の方は、手当が支給停止になる場合があります。詳しくは、児童扶養手当と公的年金等の併給についてをご確認ください。
申請・支給の方法
原則、申請者ご本人が来所して手続きしてください。
1.相談
- 内容によって提出していたただく書類がかわりますので、お住まいの区の区役所・北須磨支所の保健福祉課こども福祉担当の窓口にご相談ください(玉津支所・出張所では相談はできません)。
- 適正な支給を行うため、プライバシーに立ち入らざるを得ない場合があります。個人情報の保護は厳守しておりますので、質問や調査へのご理解ご協力をお願いします。
▷問い合わせ先 各区・北須磨支所保健福祉課こども福祉担当
▷提出書類 児童扶養手当申請・届出書類一式
2.申請から決定まで
- お住まいの区の区役所・北須磨支所の保健福祉課こども福祉担当の窓口へ必要書類を提出してください。
- 提出された書類を順次審査し、認定後、決定通知を送付します。
※決定通知の送付まで3か月程度かかります(書類に不備がない場合)。
※審査中に、書類の内容について改めて質問させていただくことがあります。また、内容の訂正が必要な場合、書類が不足している場合等に、連絡及び来所を依頼することがあります。
3.支給
- 認定された場合は、決定通知が届いた月以降の支払月に、申請月の翌月分からの手当が支給されます。
- 支払は年6回で、奇数月に前月までの2か月分を指定口座に振り込みます。
- 支払日は通常11日ですが、土曜・日曜・祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日となります。
- 振込時間は金融機関によって異なります。各自通帳等で振込をご確認ください。
※手当の受給資格に疑義が生じた場合は、支給を差し止める場合があります。
|
対象月 |
支払日 |
|---|---|
| 3月~4月分(2か月分) | 5月9日 (金曜) |
| 5月~6月分(2か月分) | 7月11日 (金曜) |
| 7月~8月分(2か月分) | 9月11日 (木曜) |
| 9月~10月分(2か月分) | 11月11日 (火曜) |
|
11月~12月分(2か月分) |
1月9日 |
| 1月~2月分(2か月分) | 3月11日 (水曜) |
受給開始後の手続き
原則、受給資格者ご本人が来所して手続きしてください。
※必要な書類は手続きによって異なりますので、事前にお住まいの区役所・北須磨支所の保健福祉課こども福祉担当の窓口にご確認ください。
▷問い合わせ先 各区・北須磨支所保健福祉課こども福祉担当
▷提出書類 児童扶養手当申請・届出書類一式
毎年8月に必ず提出…現況届
- 受給資格者は、毎年8月に現況届を提出することが義務付けられています。
- 現況届は、受給資格を更新するため全員に必ず提出いただく書類です。提出された書類をもとに、受給資格を審査します。
- 必要な書類を8月初旬頃に送りますので、8月末日までにお住まいの区役所・北須磨支所の保健福祉課こども福祉担当へ提出してください。代理人による受付はできません。
- 一部の方を除き、e-KOBEを利用して現況届を提出できます。
※e-KOBEを利用した手続きについての概要やQ&Aについてはこちらをご覧ください。
Q.提出を忘れた場合どうなりますか?
A.期限を過ぎても提出できます。ただし、期限までに現況届を提出されない場合は、手当の支給が遅れることや支給を差し止めることがあります。
また、3年度分提出しなければ受給資格がなくなります。
原則8月に提出…一部支給停止適用除外事由届
手当の支給開始月の初日から起算して5年、または手当の支給要件に該当することになった日の属する月の初日から起算して7年(認定請求または額改定請求をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)を経過した受給資格者は、原則、手当が約半分に減額されます。
対象者には、毎年6月頃に「一部支給停止適用除外事由届」を送付しますので、次のいずれかの適用除外事由に該当する場合は、事由に応じた必要書類を添えて、現況届提出時に提出してください。一部支給停止適用除外事由届を提出いただくことで、減額されなくなります。
- 就労している場合
- 求職活動などの自立を図るための活動をしている場合
- 身体または精神に障害がある場合
- 負傷または疾病などにより就業することが困難である場合
- 監護する児童または親族が障害・負傷・疾病・要介護状態などで介護する必要があるため就労することが困難である場合
Q.提出を忘れた場合どうなりますか?
A.期限を過ぎても提出できます。ただし、提出日が属する月の前月分までは手当が約半分に減額されます。

 次のような場合には必ずお住まいの区の区役所・北須磨支所の保健福祉課こども福祉担当への届出が必要です。
次のような場合には必ずお住まいの区の区役所・北須磨支所の保健福祉課こども福祉担当への届出が必要です。
所得の高い親兄弟等の同居・別居するようになったとき等…支給停止関係届
- 所得制限限度額より所得の高い扶養義務者と同居または別居することになったとき
⇒支給額の増減は同居または別居することになった翌月分から反映します。
- 受給資格者や同居の扶養義務者の所得申告の内容に修正があったとき
⇒支給額の増減は修正された所得によって算定される年度分に反映します(遡及あり)。
児童が増えたとき…額改定請求届(増額)
支給額は請求があった月の翌月分から変わります。
児童が減ったとき…額改定届(減額)
- 支給額は児童数が減った月の翌月分から変わります。
- 届出をしないまま手当を受給していると、児童数が減った月の翌月分からの過払分(受け取りすぎた手当)を返還していただくことになります。
児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日(政令で定める中度以上の障害の状態にある場合は20歳)に到達するときは手続き不要です。
結婚や事実婚をしたとき等、手当を受ける資格がなくなったとき…資格喪失届
次のような場合には、手当を受ける資格がなくなります。
- 受給資格者が婚姻したとき(事実婚を含む)※受給資格者が父または母の場合
- 受給資格者が児童を監護または養育しなくなったとき(児童の婚姻等)
- 受給資格者または児童が死亡したとき
- 受給資格者または児童が日本国内に住所がなくなったとき
- 児童が父と同居するようになったとき※受給資格者が母または養育者の場合
- 児童が母と同居するようになったとき※受給資格者が父の場合
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)等に入所したとき
- 児童を遺棄していた父または母から連絡等があったとき
- 拘禁されていた父または母が出所したとき
- その他、手当を受ける資格がなくなったとき
- 手当を辞退したいとき
住所が変わったとき…住所変更届
- 市内での住所変更の場合は、新しい住所地の区役所・北須磨支所の保健福祉課こども福祉担当の窓口に届け出てください(区内で住所変更した場合も同様)。
- 市外にお引越しされる場合は、元の住所地の区役所・北須磨支所の保健福祉課こども福祉担当の窓口に届け出たあと、新しい住所地の担当課にも必ず届け出てください。
- 市外から神戸市にお引越しされてきた場合は、新しい住所地の区役所・北須磨支所の保健福祉課こども福祉担当の窓口に届け出てください。
受給資格者や児童の氏名が変わったとき…氏名変更届
振込金融機関を変えるとき…支払金融機関変更届
e-KOBEを利用して支払金融機関変更や公金受取口座の登録・解除の届出が提出できます。
※e-KOBEを利用した手続きの概要については、こちらをご覧ください。
受給資格者や児童が公的年金を受給するようになったとき、金額が変わったとき…公的年金給付等受給状況届
届出をしないまま手当を受給していると、年金を受け始めた月から、受け取りすぎた手当を返還していただくことがあります。
児童扶養手当証書を紛失等したとき…証書亡失届
新しい証書を再発行し、郵送します。
マイナンバー(個人番号)および本人確認
児童扶養手当に関する各種手続きには、申請者・受給資格者ご本人の
マイナンバーを確認できる書類、および本人確認書類が必要です。
|
マイナンバー 確認書類(1点) |
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票のいずれか1点 |
|
|---|---|---|
|
本人確認書類 (1点または2点) |
1点 |
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、 障害者手帳(写真有り)等の顔写真入りのものいずれか1点 |
|
2点 |
健康保険証、児童扶養手当証書、年金手帳、住民票等の いずれか2点 |
|
いずれの書類も、氏名の記載および、生年月日または住所の記載があるもので、提示時点において有効なものに限ります。
よくある質問
児童扶養手当に関連したよくある問い合わせ内容を掲載しています。
こちらでは解決しなかった場合は、お住まいの区の区役所・北須磨支所もしくはホームページのお問い合わせフォームにお問い合わせください。
今後申請を考えている方
|
世帯状況などによって必要なものが違いますので、まずは、お住まいの区の区役所・支所の児童扶養手当担当までご相談ください。 |
|
離婚をしていない場合でも、事実確認をおこなったうえで要件を満たせばひとり親として認定される可能性があります。まずはお住まいの区役所・北須磨支所の児童扶養手当担当にご相談ください。 |
|
保護命令が出ている場合は、父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童として、児童扶養手当の要件に該当します。 |
|
児童扶養手当には所得制限があり、申請者・扶養義務者の所得から、手当を算定します。 |
受給中の方
|
児童扶養手当の振込日(定例支払日)は、奇数月の11日です。前月・前々月の手当が合わせて振り込まれます。奇数月の11日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の金融機関営業日の振り込みとなります。 なお、手当の審査中の場合(新しく申請している間や、更新手続き中など)は、手当が定例支払日に支給されないことがあります。審査が完了してからの支払いとなりますので、審査結果をお待ちください。 |
|
現況届には提出期限があります。 |
|
お住まいの区の区役所・支所の児童扶養手当の窓口で再発行手続きが可能です。 |
|
児童扶養手当受給中の方は、お手持ちの児童扶養手当証書の写しを使用してください。 |
|
5月振込分(3月~4月分手当)の場合 |
|
本人もしくは扶養義務者の所得超過で手当が停止になっているが、最近仕事を辞めて収入が減少しました。申告すれば手当はすぐに再開しますか。 |
|
手当額は前年の所得と養育費で換算されるため、直近の収入が減少してもすぐに手当は再開されません。 |
|
現況届や一部支給停止適用除外届出書の督促状は、督促状の発送時点で未提出の方に対してお送りしていますので、行き違いで届くことがあります。 |
ご注意
 婚姻等で受給資格がなくなる場合や、養育している児童数の変更等により手当額が変わる場合は、すぐに届出をしてください。届出をしないまま受給していた場合、受給資格のない期間に受け取った手当全額を一括返還していただくことになりますので、十分ご注意ください。
婚姻等で受給資格がなくなる場合や、養育している児童数の変更等により手当額が変わる場合は、すぐに届出をしてください。届出をしないまま受給していた場合、受給資格のない期間に受け取った手当全額を一括返還していただくことになりますので、十分ご注意ください。
Q.入籍していないので届け出なくてもよい?
A.婚姻には「戸籍上の婚姻関係」だけではなく、「事実上婚姻関係と同様の状態にある場合(事実婚)」も含みます。同居はもちろんのこと、頻繁に定期的な訪問があり、かつ定期的に生計費の補助を受けている場合は、事実婚となりますのですみやかに届け出てください。
上記のほか、
- 受給資格者や児童が妊娠した・相手が妊娠した
- 親兄弟以外の異性と住所が同じになる
- 住民票上の住所と実際の居住地が異なる
- 扶養義務者等と同居するようになる
- 受給資格者や児童が公的年金等を受給することになる
などの生活状況の変化があれば、別途届出が必要です。すみやかにお住まいの区の区・北須磨支所の保健福祉課こども福祉担当の窓口にご相談ください。
 偽りその他の不正な手段により手当の支給を受けた場合、児童扶養手当法に基づき、受け取った手当を返還していただくことや、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
偽りその他の不正な手段により手当の支給を受けた場合、児童扶養手当法に基づき、受け取った手当を返還していただくことや、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
 適正な支給を行うため、プライバシーに立ち入らざるを得ない場合があります。個人情報の保護は厳守しておりますので、質問や調査へのご理解ご協力をお願いします。
適正な支給を行うため、プライバシーに立ち入らざるを得ない場合があります。個人情報の保護は厳守しておりますので、質問や調査へのご理解ご協力をお願いします。
