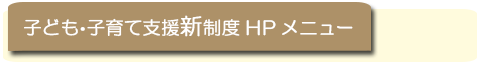ホーム > 子育て > 乳幼児期(0~5歳) > よくある質問
よくある質問
最終更新日:2024年7月26日
ページID:3637
ここから本文です。
本ページでは、子育て等について皆さまから多くお寄せいただくご質問について、Q&Aを掲載しております。
ご確認のうえ、該当する回答が見当たらない場合は、別途メール等でお問合せください。
よくある質問と回答を検索する
申請手続き時のよくある質問を検索できます。キーワードを入れて検索してください。
よくある質問:「保育料」「空き状況」「意見書」
入園・入所について
Q:幼稚園・保育所などに入園・入所するにはどうしたらいいの?
幼稚園・保育所などの入園・入所を希望される場合、保育の必要性の認定(「教育・保育給付認定」といいます。)を受けていただくことになります。
具体的には、保育所や認定こども園、地域型保育事業所への入所を希望される(お子さんの保育を必要とする)方は、保育を必要とする事情が分かるものを添えて、区役所(北須磨支所・北神保健福祉課を含む。)に教育・保育給付認定の申請書類などを提出していただき、区役所で保護者の利用希望を踏まえ、利用の調整を行います。
また、幼稚園の入園を希望される方は、これまでと同様に各幼稚園に直接申込みをしていただき、幼稚園を通じて教育・保育給付認定の申請書類を提出していただくことになりますが、その幼稚園が認定こども園に変わる場合には、(長い時間の利用を希望される子どもさんなど、)区役所での手続きが必要となる場合があります。
教育・保育給付認定の手続きについては、下記ホームページをご覧ください。
申請・利用申込み方法 ー認定申請と利用申込の概要 申請方法ー
Q:年度途中の保育利用の申込みはいつから可能なの?
原則として、前々月中(例:6月入園希望の場合は4月中)に申請をしてください。
Q:認定こども園では、だれでも朝~夕まで子どもを預けることができるの?
認定こども園は、園によって【1】朝~昼過ぎまでを日常的に利用する場合(3-5歳)、【2】朝~夕までを日常的に利用する場合(0-5歳)の2つの利用方法があります。【2】朝~夕までを日常的に利用する場合は、保育所に入所する場合と同じように、利用するための要件があります。なお、【1】朝~昼すぎまでを日常的に利用する場合でも、利用時間の前後や長期休業中に希望する園児をお預かりする「預かり保育」を別途利用していただくことができます。
認定区分について
Q:保育認定(3号認定)の子どもが3歳になって、保育認定(2号認定)になる時は改めて手続きが必要になるの?
満3歳になり、保育認定(3号認定)から保育認定(2号認定)になる際は、神戸市が認定の変更を行うので、世帯や就労の状況に変更がなければ、特段、保護者の方が改めて認定の申請をする必要はありません。
Q:認定こども園は、就労していなくても利用できるの?
認定こども園の中には、教育標準時間(1号認定)を設けず、保育時間(2号・3号認定)の受入のみ行う施設もあります。
これら教育標準時間(1号認定)の利用枠を設けない認定こども園に入園する際には、就労している等の保育を必要とする事由が必要となります。
なお、入園後に、保育時間(2号認定)から教育標準時間(1号認定)に区分を変更したい場合には、施設の状況に応じて、期間を限定して教育標準時間(1号認定)としての利用が認められる場合もあります。(保育時間(2号認定)の利用枠に戻ることを保証するものではありません)
Q:認定こども園で1号認定で入園したが、仕事を始めたため、途中から2号に変わることはできるの?
保護者の就労状況が変化しても、継続して同一の施設で教育・保育を受けることが認定こども園のメリットのひとつであることから、利用定員に空きがある場合はもちろんのこと、園の状況に応じて一定の定員超過での利用が認められる場合もあります。
なお、新規の利用希望の子どもを含め、定員超過の場合など、希望人数が施設・事業所の受入能力を上回り、希望者全員の保育利用が困難である場合には、区役所にて選考を行うことになっています。
利用者負担額(保育料)について
Q:幼児教育・保育の無償化で利用者負担額(保育料)はどうなるの?
令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が始まり、幼稚園や保育所、認定こども園などを利用する3~5歳児の保育料が無償となりました。また、住民税非課税世帯は0~2歳児についても無償となりました。
幼児教育・保育無償化の概要
Q:利用者負担額(保育料)はどのように決められているの?
利用される方に負担いただく利用者負担額(保育料)は、現行の負担水準をもとに国が定める基準を上限とし、所得に応じて神戸市が定めることとされています。
Q:施設によって利用者負担額(保育料)は違うの?
神戸市が、認定区分ごとに市民税額の階層区分別の利用者負担額(保育料)を定めます。そのため、同じ認定区分と階層区分であれば、どの施設・事業所でも同一の利用者負担額(保育料)です。
なお、施設や事業所により給食費や園バス代、制服代、施設整備費等が別途必要になる場合もありますので、詳細は各施設・事業所にお問い合わせください。