葺合・地名ものがたり
最終更新日:2023年9月14日
ここから本文です。
「地図と地名の由来」(葺合市場商店街連絡協議会より)
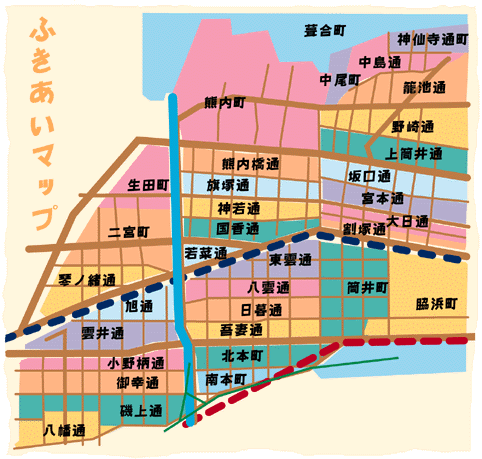
熊内町(1905年)熊内橋通(1903年)
旧熊内村。くまは神で神内で生田神社の神領?くまは隈で奥まったところ?また朝霧で雲内?
畑作が盛んで大根の産地として熊内大根は有名。また若菜のすずしろは大根の若葉。
熊内橋は今の生田川の布引橋のことでこれが完成したのにちなみ。
生田町(1899年)
旧生田村。生田川はフラワーロードから付け替えたのもだが江戸時代以前も現在と同じ流域を流れていたらしく生田村は生田神社の続きにあったので。
若菜通(1901年)
「旅人の道さまたげに摘むものは生田の小野のわかななりけり」(師輔『堀川首』)から。 醍醐天皇の御代、春の七草を各地から集めさせたところ葺屋荘で採れたものが秀逸で天皇より「若菜の里」と言う名を賜り生田の若菜と呼ばれたことから。
二宮町(1899年)
二宮神社から。二宮神社は葺屋荘全体の産土神。
布引町(1899年)
布引の滝への道筋から。
琴ノ緒町(1899年)
「松の音を琴に調ぶる山嵐は滝の糸をやすけて弾くらむ」(紀貫之)から。元々コトノオという小字名で呼ばれていたとも。
旭通(1899年)
「呉竹の夜の間の雨に洗ひほして朝日に晒す布引の滝(西園寺実氏1215)にちなんで。同じ時に付けた日暮、雲井、八雲などと対応させている。
雲井通(1899年)
「雲井よりつらぬき懸る白玉を誰れ布引の滝といひけむ」(藤原隆家)他による。
小野柄通(1899年)
平安時代より生田の小野として有名。この南の小野浜に江戸末期、勝海舟の海軍操連所を設置。柄は「分け入りし幾多の斧の柄もここに朽ちしや果てむ布引の滝」(加茂季鷹)から。
御幸通(1899年)
生田神社の御神体が脇浜村へ渡御する巡幸道だったため江戸時代から御幸道と呼ばれていた。
八雲通(1901年)
古歌(素戔鳴尊?)の「八雲立つ出雲八重垣妻ごみに八重垣つくるその八重垣を」から。
北本町(1901年)
西国街道浜街道に沿いその北を北本町南側を、南本町と名づけた。当時新しく名づけた地区の中では古くから開けていたのを反映させたらしい。
東雲通(1901年)
「みつか夜のまだ臥し慣れぬ芦の屋のつまもあらはに明る東雲」(藤原隆家)から。
日暮通(1899年)
「布引の滝見て今日の日は暮れぬ一夜宿かせ峰の笹岳」(澄覚法親王)から。
吾妻通(1901年)
葺合町の一部が耕地整理されて新地名に。
春日野通
居留地の設置に伴い小野浜に明治2年外国人墓地が設置されたが手狭となった。
籠池通辺りにあった春日明神からその辺りを春日野と呼ばれていたが明治32年外人墓地として春日野墓地ができたのに伴い明治36年西国街道まで南北の道路を作った。
これを春日野道と呼ぶようになった。
脇浜町(1906年)
旧脇浜村。敏馬崎(みねまさき)の脇にある浜から。
神功皇后朝鮮遠征の帰途、雨風をしのぐためにここに上陸し軍船の脇盾を外し仮の高御蔵としたことから脇盾浜となり転じて脇浜となったと言う伝説も。
割塚通(1916年)
昔、古墳があったが豊臣秀吉の大坂城築城に際し石垣用に大石を運び出し壊してしまった。
この後、割れ塚・割塚と呼ばれるようになったことから。
この古墳布敷首の墓と言われているが被葬者は明らかでない。
大日通(1916年)
滝勝寺の寺、大日寺があったことから。
宮本通(1916年)
旧筒井村の本村(中心)。筒井八幡宮の元と言う意味で。
坂口通(1916年)
古くから摩耶山の登り口にあたり坂口と呼ばれていた。
上筒井通(1916年)筒井町(1906年)
旧筒井村。筒井八幡の境内にあった筒形の井戸が名前の由来。
平安末期すでにこの辺りの名前になっていたらしい。筒井の北が上筒井、南が下筒井だったが下筒井町に大正9年阪急が大坂~上筒井間に開通、新興住宅に。
野崎通(1916年)
この辺りは高台にあり高台を野先と呼ぶことから野崎と言われていた。
籠池通(1910年?)
籠池は漏水の多い池のこと。籠池と呼ばれる池があった。
中島通(1916年)
中尾村中島から。詳細は不明。
中尾町(1926年)
旧中尾村中尾、ナカオはナゴ、ナゴワと共に山の緩斜面をさす言葉。
葺合町(1899年)
旧葺合町全体の内新町名を付けて独立してしまったな残りの地域。このため山間部が多い。
神仙寺通(1916年)
滝勝寺の末寺、神仙寺があったことから。
神若通(1903年)
滝勝寺の塔頭で神若寺があったので。
旗塚通(1899年)
旗塚と呼ばれる古墳が6丁目にあったこちから。明治30年ころ道路整備のため整地。
国香通(1903年)
「布引きの滝津瀬かけて難波津や梅か香おくる春の浦風」(澄覚法親王)による。